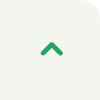どうして歯石はできるの?
どうして歯石はできるの?
こんにちは。戸塚区の歯医者、酒井歯科診療所、院長の酒井穣です。
当院では、歯周病治療、およびその後の予防歯科に力を入れています。
その中の歯石取り、口の中のクリーニングは非常に重要です。
初診時は、たいてい皆さんのお口の中はプラーク、歯石などで汚れていますので、基本的には治療に取り掛かる前にお口のクリーニングから行います。
プラークは歯磨きで落ちるくらいなので、割合簡単に取れますが、歯石は歯ブラシでは取れません。
そこで専門の器具で歯石を取るわけですが、そもそも歯石はどうしてできるのでしょうか?
▪️歯石の成り立ち
最初はプラークから始まります。
歯と歯ぐきの境目には、深さが1〜2mmの歯肉溝(歯周ポケット)という溝があります。
お口の中を不潔にしていると、歯肉溝にバイオフィルム(プラーク)ができます。
バイオフィルムは、虫歯菌や歯周病菌などの細菌のかたまりです。
不潔な状態が続くと、バイオフィルムはどんどん増えます。
このプラークをブラッシングで除去しないで長いこと放っておくと、
唾液のカルシウム成分が沈着して“歯石“になります。
バイオフィルムによって歯ぐきに炎症が起き、歯肉が赤く腫れます。
これが、歯周病のはじまりの歯肉炎です。
歯肉炎を放っておくと、知らないうちに歯ぐきの内部にまで炎症が広がり、歯と歯ぐきのつなぎ目や、歯を支えている骨が破壊されて、歯周炎になります。歯肉炎と歯周炎を合わせて、「歯周病」と呼んでいます。
「毎食後、毎日しっかり歯磨きをしているから歯石はつかない」と、歯磨きに自信のある方は思うかもしれません。
歯の隙間も気をつけてしっかりと磨いているはずなのに、どうして歯石として溜まってしまうのか不思議と思われる方は多いのではないでしょうか。
当院では、ブラッシング指導の際、磨き残しをわかりやすくするために、お口の汚れを染め出して、歯ブラシの苦手な部位を確認します。
程度の差はありますが、完璧に磨けてる方はめったにいません。
概ね、歯と歯ぐきの境目、歯と歯の間が赤く染まることが多いです。
唾液の出口に近い下の前歯の裏側や、上の奥歯の頬側のところは唾液成分が沈着して歯石がつきやすいです。
▪️歯石の種類
歯石ができる場所によって2種類あります。
歯石ができる仕組みは、歯ぐきの上にできるか、下にできるかで異なります。
【歯ぐきの上にできる歯石】
歯ぐきより上にできる歯石を「歯肉縁上歯石(しにくえんじょうしせき)」といいます。
歯の裏側には唾液が出るところがあり、そこから出た唾液とカルシウム成分が結びつくことで、歯垢が石灰化という、石のように固まる現象が起こります。
これが溜まることで“歯石“となります。
歯の表面はエナメル質に覆われています。このエナメル質はツルツルしているため、ここについた歯石は比較的除去しやすい歯石です。
・特徴
色は黄白色、灰白色
プラーク(歯垢)が原因で、唾液によって石灰化する。
縁下歯石に比べると量が多く、形成が早い。
縁下歯石よりやわらかく、比較的簡単に除去できる。
歯肉炎の原因になる。
【歯ぐきの下にできる歯石】
歯ぐきより下にできる歯石を「歯肉縁下歯石(しにくえんかしせき)」といいます。
唾液と関係する歯肉縁上歯石とは違い、歯と歯ぐきの間から滲み出る“滲出液“というものと、カルシウム成分が結びつき、歯垢などが石灰化し固まってできる歯石です。
歯ぐきの下にこびりついているため、除去するのが難しく、痛みもあります。
・特徴
色は黒褐色。これは血液の成分を取り込んでできるためです。
歯肉からの出血が原因。
歯肉溝滲出液が石灰化につよく関与している。
縁上歯石に比べると量は多くないが、硬く、除去が困難である。
歯周病の原因になる。
歯垢というのは、汚れだけではなく、90%以上が虫歯菌や歯周病菌といった細菌なのです。
細菌の集まりである歯垢が固まったのが歯石です。
▪️歯周病予防のために
・個人の特性に合った毎日の歯磨き
・歯科医院で行う定期的なメンテナンス
・生活習慣、食生活、嗜好
・唾液分泌量、口腔乾燥症の有無
歯周病は、全身への影響も報告されています。
誤嚥性肺炎、心疾患、脳卒中、高血圧、糖尿病等。
当医院では、健康指導も行っております。
とくに高齢の方においては、フレイルとの関連が注目されています。
「お口の健康から、全身の健康へ」
お口の健康を保つことは、全身の免疫力を高めます。
お口の健康をサポートすることで、地域医療への貢献を、酒井歯科診療所は目指しています。